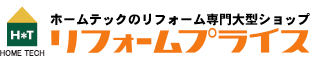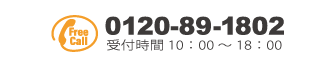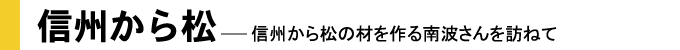 |
|||
 |
|||
|
|||
唐松は標高600メートル以上の場所に生えます。そして、信州から松は全国の唐松の先祖でもあります。 |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
  信州から松でもっとも目に付く特徴といえば、その独特の赤みがかった美しい色合いでしょう。 特に木裏と呼ばれる樹心に近い部分はその色もより鮮やかで、また組織もしっかりしている為に変形を起こしにくくなっています。 強度と美しさを兼ね備えた信州から松は、床や壁など家の様々な箇所に用いることができます。 ただし、今現在は梁(はり)や框(かまち)といった大きな部材をから松から取る事は難しくなっています。戦後植えられたから松があと10年程で利用可能となります。 今、私たちが手にする天然木は、輸入材がほとんどです。 残念なことに、輸入材の多くは中国などから盗伐されたもので、木自体の状態をよく見ずに切り出して使っていたり、仕上げが美しくないものも少なくありません。 日本には産地の方が大切に守り受け継いできた『日本の木』があります。 沢山の人々の想いが込められ、木の良さを極限まで引き出された材となり、私たちの元へと届けられる日を待っています。 |